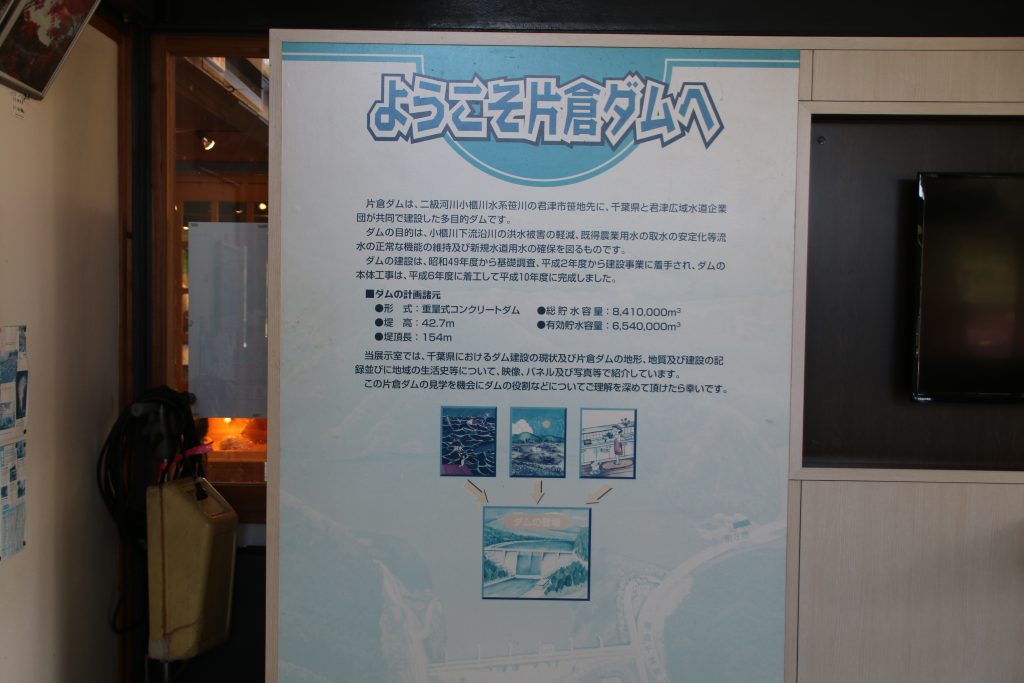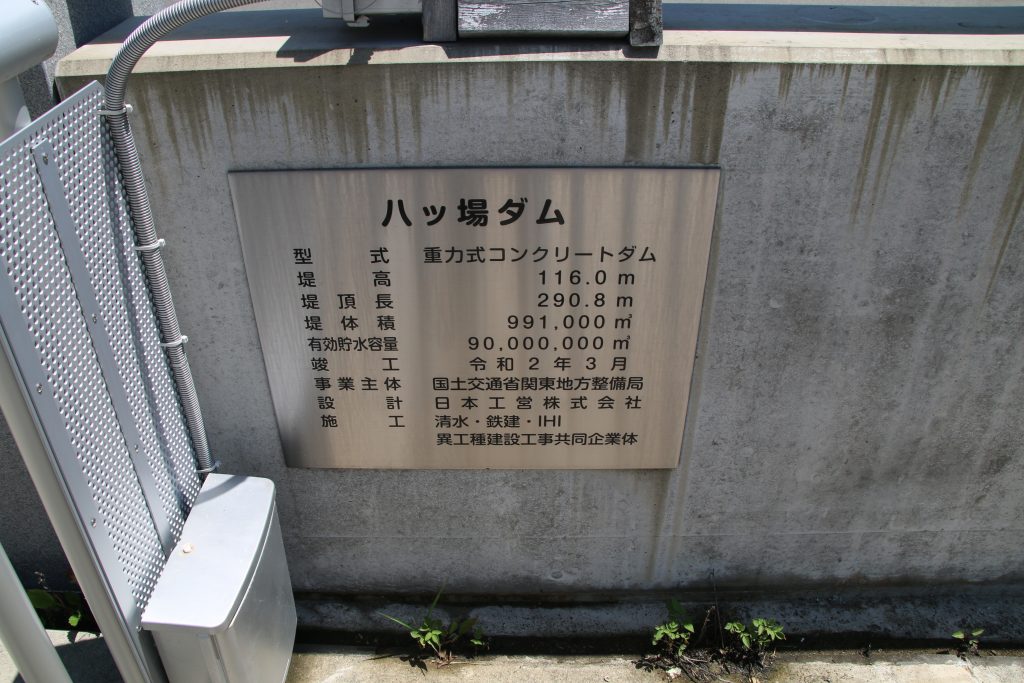五十里ダム
 五十里ダムを展望広場から望む(2023年4月)
五十里ダムを展望広場から望む(2023年4月)
五十里ダムは利根川水系男鹿川に建設され昭和31年の竣工当時堤体高日本最高の112mを誇る大ダムです。形式は重力式コンクリートダムで目的はFNPの多目的ダムです。
ダム関連で「物部長穂」氏の名前はよく出てきますがこのダムも氏が発表した「河水統制計画」に当初から含まれていました。現在より下流に建設を予定しましたが、調査で多数の断層が発見され建設が断念されます。昭和16年には現在地での建設が検討されましたが、戦争で中断。同時期に計画され、五十里ダム竣工の翌年昭和32年に竣工した小河内ダムと経緯が似ています。
昭和31年には佐久間ダム 元(静岡)も竣工しており堤体高日本一の座は竣工すぐに譲ることになります。この時期は太平洋戦争で中断ー再開していた日本のダムインフラ開発の竣工が続きました。更にはこの年には黒部ダムが着工しており昭和31年は日本のダム史において重要な年です。
ダムの放流調整能力向上のため、いくつかの改良工事を経ています。大規模なのは旧クレストゲートの機能拡張と2つのコンジットゲートの新設です。上の写真で隠れていますが、天端直下のクレストゲート3門、旧コンジットゲートが元々の設備でしたが外見からも追加されたクレストゲート用の導水管が目立ちます。
旧コンジットゲートは流量調整ができないものであったために、ゲート奥にホロージェットバルブが追加(リンクは参照URL)されました。更に写真手前中段辺りに見える導水管と2門の新コンジットゲートを追加する大工事をダムを運用しながら行なって現在の姿になっています。
現在でも活躍しており、これについてはまたの機会に紹介します。
桜の前に水神碑、慰霊碑、竣工50年記念碑
 五十里ダムの水神、慰霊碑、竣工50年記念碑(2023年4月)
五十里ダムの水神、慰霊碑、竣工50年記念碑(2023年4月)
左から水神碑、慰霊碑、竣工50年記念碑です。水神碑はあるダムとないダムがありますが何かの基準があるのかはわかりません。
慰霊碑は新しいダムには少なくなりますが、建設中に殉職者を出したダムでは必ずあるものと思われます。特に昭和50年以前に竣工したダム(相模ダム、小河内ダムなど)では建設中に多くの方が亡くなっているケースが多く五十里ダムもその一つです。
竣工が昭和31年(1956年)なので竣工50年は2006年。記事を書いているのが2023年で67年目、還暦を過ぎています。
なお奥に見えているゲートは新設された発電用の選択取水設備ではないかと思われます。五十里ダム、施設の追加工事が多くて他記事でも設備があったりなかったりです。
五十里ダム天端への入口
 五十里ダムの天端入口(2023年4月)
五十里ダムの天端入口(2023年4月)
五十里ダムの標識と天端入口です。車両通行止めですが、徒歩での立ち入りは問題ありません。なお、手前+奥の山に雪が降っているのがわかると思います。4月中旬というのにこの日は寒かった。
五十里ダム天端から下流を望む
 五十里ダム天端から下流を望む(2023年4月)
五十里ダム天端から下流を望む(2023年4月)
天端から下流を望むと副ダムが見えます。副ダム右側には遊歩道らしきものが見えています。一般立ち入り可能な場所ならダム堤体がよく見えそうですが、今回は残り時間のことも考えて後ろ髪を引かれながらも確認できず。
山に隠れて下流には川治温泉があります。奥に見えている山は高く見えますが標高約900mの(たぶん)無名峰です。標高の割に奥多摩や奥秩父より寒いです。
五十里ダム天端から五十里湖を望む
 五十里ダム天端から五十里湖を望む(2023年4月)
五十里ダム天端から五十里湖を望む(2023年4月)
五十里ダムのダム湖は五十里湖と名付けられています。ダム湖面はかなり狭い印象で、この点は同じ利根川水系でも矢木沢ダムの奥利根湖、奈良俣ダムの奈良俣湖の風景とやや異なります。実際、五十里ダムの貯水量はこの二つのダムと比較すると矢木沢ダムの4分の1強、奈良俣ダムの半分程度です。この弱点を補強するために、上流に建設されたのがこの後に訪問する湯西川ダムです。
ダム放流操作プレイができるダムコン模型
 操作を体験出来るダムコン模型(2023年4月)
操作を体験出来るダムコン模型(2023年4月)
五十里ダムの管理事務所に併設された展示館にはダム放流操作を体感できるダムコン模型があります。放流操作を進めていくと実機と同じと思われる警告音が響きはじめ、ゲート開放操作をすると下のように放流映像が流れるというなかなか凝った仕様です。
 ダムコン模型で放流操作をした時の映像(2023年4月)
ダムコン模型で放流操作をした時の映像(2023年4月)
雨量計の動作展示
五十里ダムの展示でもう一つ面白いのが雨量計です。本物の雨量計は計量マスが外枠の中に入っていて動きを見ることはできませんが、外枠を透明にして計量マスが左右に傾く様子を見える展示があります。
また小型のポンプを用いて水を循環させているのでスタートさせると計量マスが1mm毎の降水で傾く様子を連続的に確認できます。
この二つの展示はもしかするとダムの展示を担当した人が工作したのか?などと思ったり。
色々見所が多く全てを周り切れませんでしたが、次の湯西川ダムに向かいます。