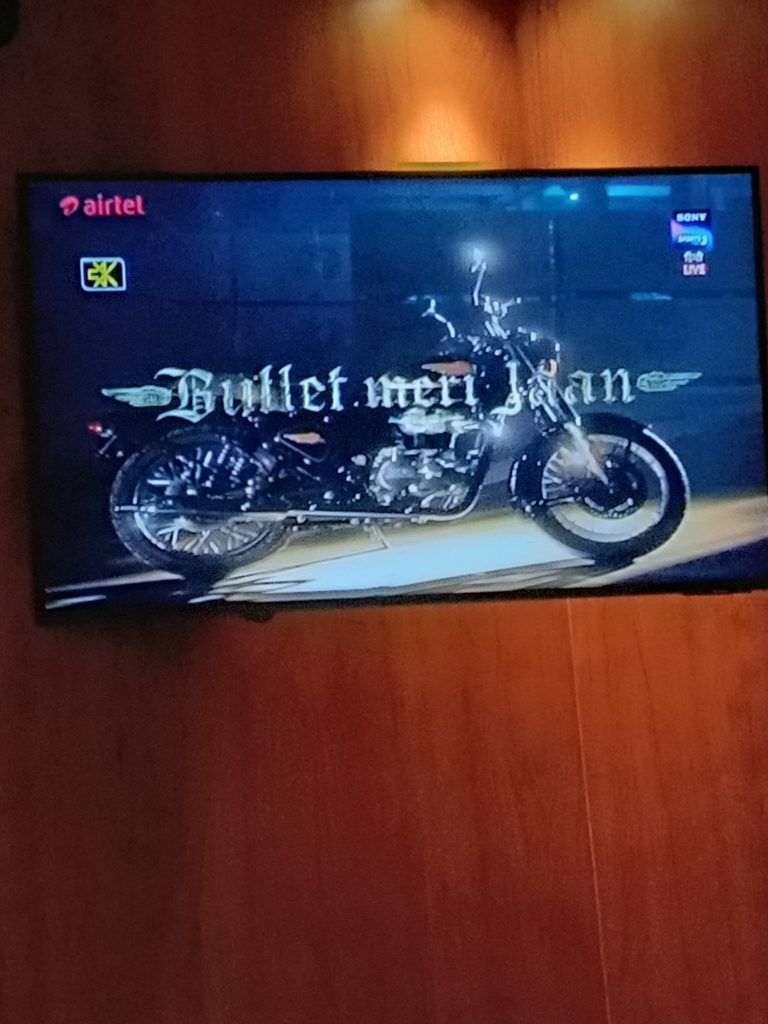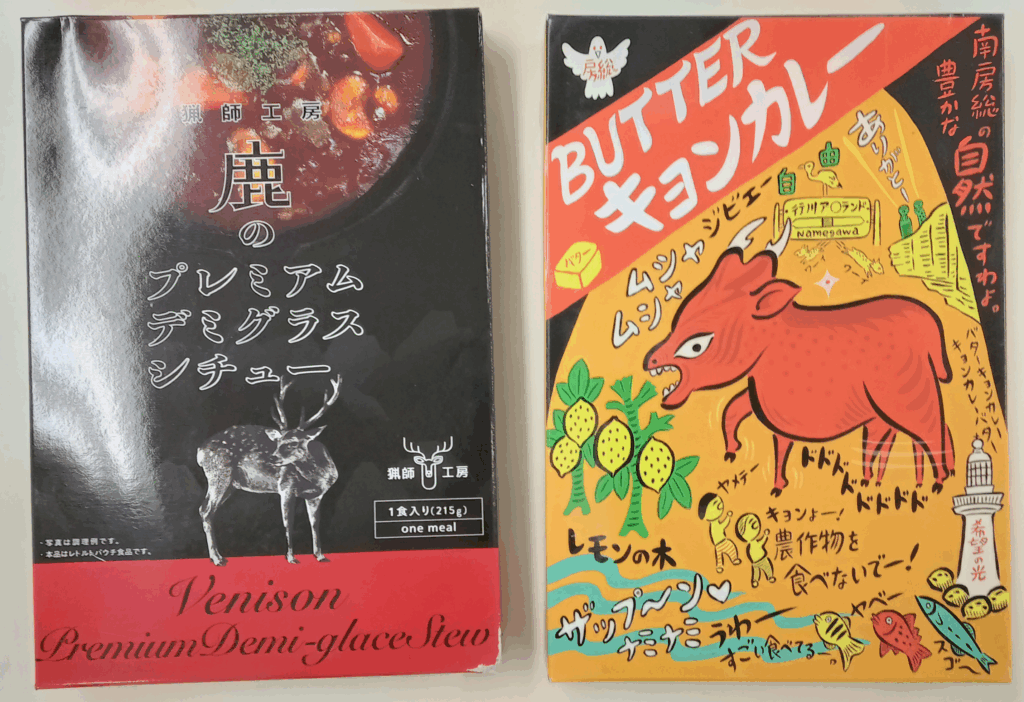2019年11月NC750S納車から6年目のレビュー
まず特筆するべきは大きな故障なく来たこと、そして小さな故障もほとんどありません。コストパフォーマンスに優れた車体は維持でもコストパフォーマンスが高いのです。
消耗品、オイルはまめに交換、チェーン+スプロケット1回、バッテリー1回、ステムベアリング1回、前後タイヤ2回、走行距離のわりに少ない。チェーン+スプロケットは一度錆びさせたダメージが大きくコマの固着が発生し交換となりました。(シール)チェーン注油は意味がないという意見もありますが、錆びはやはり大敵なので最低限注油というか表面のオイル膜を保持するのは寿命の観点から大事だと思います。
タイヤはとても長持ちします。一般的にはリアタイヤが先に減ることが多いですが、NC750Sの場合フロントタイヤから先に減ります。私の乗り方の影響もあるかもしれませんが、独特の低出力、前傾エンジンによる前寄り荷重などが影響していると思われます。タイヤの種類や走る場所によっても異なりますが20000kmに1回の交換はかなり驚異的です。
 柳沢峠のススキとNC750S
柳沢峠のススキとNC750S
50000km乗って変わらない・変わった点のレビュー
変わった点。少し燃費は悪くなったかもしれません。とはいえ、28km/lが26km/lになった位の差です。もしかしたら…管理人の体重増加分の可能性もあります。またこれはNCではなく管理人自身の変化ですが、少しブレーキを使うのが上手になったと思います。いわゆるナメ掛けが1段階しかなかったのが3段階くらいに増えたイメージです。少しでも安全運転に繋がるように意識しています。後は…同車種に会う機会がほとんどなくなりました。兄弟のNC750Xは割と会うのですが2020年に生産終了したNC750Sにはめっきり会う機会が少なくなりました。(というかほぼない。)
変わらない点。燃費は多少悪くなったとはいえ十分に良いですし、故障もほとんどありません。サスペンションやブレーキなども特に問題は起こってません。出力の低下も感じられませんし、排気音も変わっていないと思います。2輪で6年ちょっと経過し50000km走ればどこかヘタって来そうなものですが全く感じられません。100000kmも問題なく行けるのでは…という感触です。
 山梨県甲州市のブドウ畑とNC750S
山梨県甲州市のブドウ畑とNC750S
まだまだ安全運転で乗ろうと思う
実は50000kmは5年目には達成するつもりでしたが、いくつかの理由で伸びました。一番大きな理由は、仕事上の大きな変化があったことで体力と体調を損ねた時期があったことです。そのほかではXL883Nの面倒も見ていることです。これは嬉しいことですけど。
2019年から今までなのでやはりいろいろなことがありましたね。前述の仕事上の変化にも関係しますがCOVID-19の影響は本当に大きかったです。またその間にも管理人も少し年を取って体力が低下しているのは否めません。一日NC750Sと付き合うには坐骨神経痛対策のロキソニンが手放せなくなりました。また二日連続の丸一日走行は次の日の仕事に差し支えるため自重するようになりました、大人ですからね。
でも、この間にはさまざまな出会いも経験し楽しい思いも少なくありません。これからも安全運転で少しでも上手に乗れるように意識しながら楽しい思い出を積み重ねていこうと思います。
 鈴倉山林道でNC750S
鈴倉山林道でNC750S
直近のツーリングでは鈴倉山林道を竹森から三富に抜けました。正直、三富側の数キロは路面状態が良いとはいえず少々肝を冷やしました。写真撮影の場所は舗装がきれいで明るく映っていますが…。
今日はこの荒れた道で泥で汚れていたので洗車+チェーン注油しました。機嫌を直してくれたのか街乗りで燃費が28km/l程度になっていました。手入れは大事?ブログも時々アップしていきますので時々読んでいただけると嬉しいかぎり。