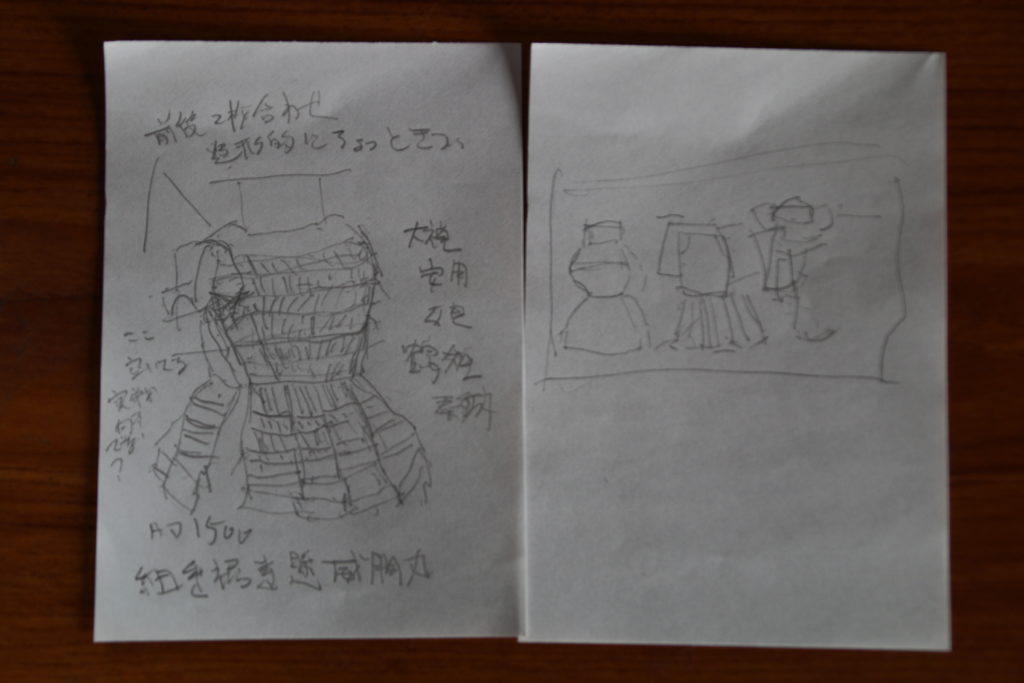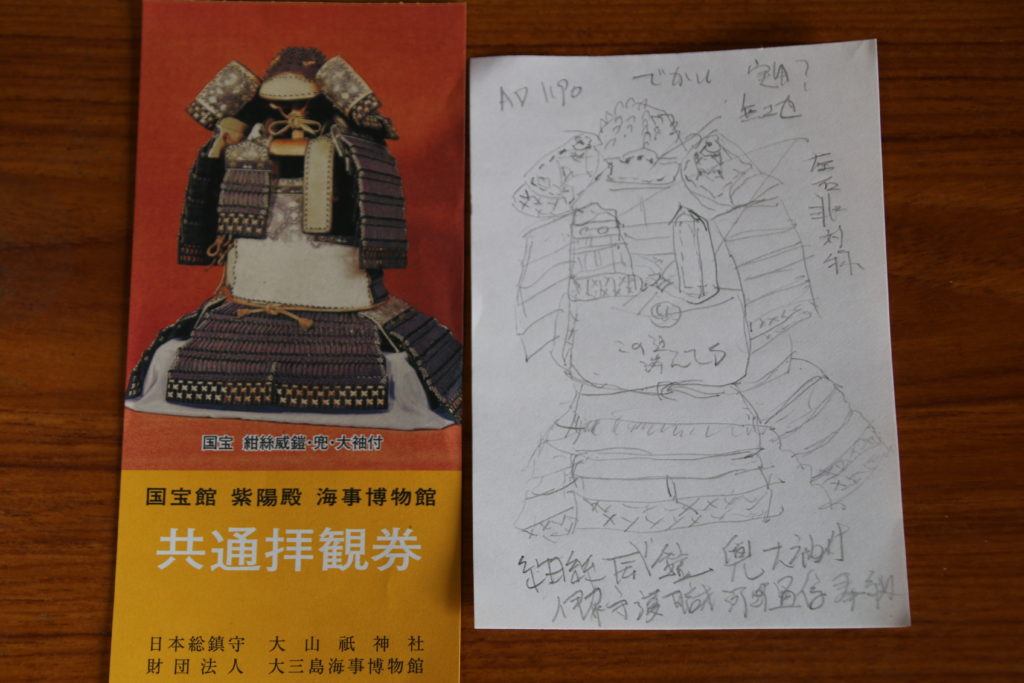デザイン ★★★★ モンキー125との差別化が…
エンジン ★★★★★ 十分なキビキビ感
ブレーキ ★★★ リアブレーキはもう少し利いて欲しい
ミッション★★★★ 熟成の域、時々シフト迷子で満点は避けた
使い勝手 ★★★ シートはもう少し長さが欲しい、タンク小さい
コスト ★★★★★ 一日走り回っても燃料代1000円以下 素晴らしい
価格 ★★★ 実用的かつ個性的ですが安くは…ない
若干辛めの採点ですが管理人としては好感を持てました。総合は★★★★+αの印象です。
Honda ST125 DAX(ダックス125)はモンキー125とCT125ハンターカブの中間的存在
結論から言うと、走りに重点を置いたモンキー125と積載性・遊び心に重点を置いたCT125ハンターカブの良くも悪くも中間的な印象。5段の変速器が設定され走り重視のモンキーに比べると若干ゆったりした印象(4段変速)ですが、同じ構成のCT125に比べると重量が10kg程度軽いことや全体的に小柄(軸距で60mm小さい)ことで軽快感はダックス125が勝ります。
積載性は積載の鬼CT125ハンターカブには当たり前ですが及びません。ただタンデムシートの後ろ部分は小型の荷台としても使用できるのでノーマルでもある程度の積載性が確保されています。フックをかける場所もそこそこあって困りません。
そして、この3車で唯一ノーマルでタンデムが考慮されているのがダックス125。友人とちょっとしたお出かけを二人乗りで…という楽しみがあるのはダックス125の個性です。
 ダックス125を左側から(2025年1月)
ダックス125を左側から(2025年1月)
DAX125のここが〇、ここが×
少ないのでここが×から。まず前輪の挙動が独特で着座位置で極端に変わります。前目に乗っているときは気になりませんが、後ろ目にドカッと座ると若干跳ねる印象です。贅沢を言えばフロントサスはもう少しストローク長めで柔らかいのが良いように感じました。
×二つ目はミラーと動線の位置関係が良くないです。乗り降りする際に少しぶつかるとミラーが動くので都度直す必要があります。固定も固めかと思えば動き始めるとクルッと動くので微調整が文字通り微妙です。ホーンも干渉しやすく、ちょっとしたタイミングでピッて鳴らしてしまいます。また位置関係でいうとサイドスタンドの出し口も少し分かりにくいかも。
△三つめはタンク容量が少ない。3.8lは燃費60km/lとしても航続距離224km。ツーリングには少し物足りない航続距離です。
〇は何より小気味の良い走り。CT125よりも明らかにきびきびと走ります。法定速度+αまで素直に加速するので流れの早い道でも戸惑うことがありません。
またノーマルでタンデムor荷物積載可能な点も好感が高い。タンデムバーは若干小さめですが、近距離であれば問題ないと思われます。惜しむらくはシート+タンデムバーが+5~10cm後ろ向けの長さがあるとタンデム+荷物積載がよりよくなったのではと感じました。
デザインは右側のみダックスロゴのST125ステッカーが貼られているなどなかなか気が利いています。またハンターカブと似た、上出しのマフラーも存在感があって管理人の好みです。
往年のDAXファンが見ると、フロント周りがモンキー125と同じでは…という印象を受けるかもしれません。これは旧DAXに比べると胴(シートからステムまで)が太くなり、エンジンも大きくなっているので胴下のスペースが狭くなっているためです。
ここは完全な好みですが、管理人は悪くないと思います。
 DAX125を右側から(2025年1月)
DAX125を右側から(2025年1月)
結局おすすめ出来る人、できない人
お勧めできない人はロングツーリングが主体(タンク小さい)、荷物をたくさん載せたい(積載性が高いとは言えない)の特徴がある人です。ロングツーリングならモンキー125またはCT125ハンターカブ、荷物載せるならCT125ハンターカブをお勧めします。
お勧めできる人はデザインが好みで、絶対的なスピードに拘らず、街中や近距離ツーリングを走り、時々小さめの荷物を載せたりタンデムでどこか出かけたりという人です。ツーリングは大排気量のメイン機担当として、2台目にDAX125の選択肢はちょっと贅沢ですが良い組み合わせと思います。
普通二輪免許を持っている場合、排気量、価格でPCX160と比較する向きもあるようですが…コンセプトもデザインも違いすぎて一方が「刺さる」人にはもう一方は候補に挙がらないように思います。
なお、燃費は322km走行で5.77l給油(2回)で59.3km/lでした。